
「フローリング」専門の剣道家と話や稽古をする機会を得ました。
以下のようなホームページを作っている方です。
> [剣道場 床建築工房] http://kendoujou.com/
このページだけでも、剣道場の床についての情熱、剣道への情熱がひしひしと伝わってきます。
また、いろいろな道場の調査にいっているページなんかもまた、スゴいですね!!!
そして、実際にお話をするとね、、、ヲタクっぷり、、、脱帽です。
今時点、もしかするとわたしは組織的に情報を配信できる可能性もある立場にあったりもしますし、、、剣道をする人にも床についてもかんがえてもらえればと、今回思いつくことを、まずは、エヴァにならって「序」として書き連ねておいてみたいと思います。
今回は、松、杉、檜、桜、、、どの木材とか、どういう工法がとか、そういう話ではなくかきます、、、それらは今後、彼らといろいろと話しをして勉強してから、発展したネタになるとイイなぁと思っています。
とにかく、、、道具は、個々の感性、趣向で、個々人で選ぶことはまだできますが、床は選ぶことはまずできないのだから、、、というのが今回のネタの要約になりましょうか。
床に関しては、私自身、彼らほど詳しくはないものの、、、
スギの一枚板の道場でTKB時代10年強もも過ごしたこともあり、いろいろとその意義・効用とかも聞かされたこともあります。
TKBを離れてからは、体育館という剣道にとってはあまりよくない環境をはじめ、いろいろなところでやっています。
これは正直、身体にもよくなく、、、この変化から一時期踵など身体を壊したり、技術にもよくなかったような気がします……。
そして、いまの勤務先では、数年前、武道用床の集成材に張替え、体育のセンセの立場から武道用ウレタン塗装をしなくてはならず、、、ここ短期間でケガが多く出たので、塗装を剥がしていわゆる白木の状態、最近の技術としてオイルフィニッシュにしたとか(いまの弊社道場は非常にいいというレベルにあるようです)、、、
そういう経緯もあり、今回、彼に会うのが楽しみで、会ったら会ったで、本当に楽しい時間だったのです。
そして今回、フローリングと剣道をこよなく愛するヒトたちにいろいろと伺うと、、、
一枚板は集成材より高価だから、、、というわけではないということ、、、
バネによる衝撃緩衝は、振動があり身体に戻ってくるので身体への影響があるとか、、、
板そのものや構造などの深い所、それから業界の流通の問題といろいろとありますね。
塗装や柔らかさの問題はは各種大会にいろいろと参加させてもらっていた時に選手としてデリケート(っぽく)になっていたころから、、、試合が少なくなったいまでも、そのようなプレイヤーとして必要であろうと感覚はつねにもちつづけております。
まぁ、わたしは大した選手でもなく、結局調整しきれないことも多々ありましたし、一流でしたらいちいち考えずに瞬時に的確に対応していることかもしれませんね。
大会ごとで床の状態が違うのです、、、床の引っ掛かりや滑りという観点からは、足の左右前後の幅の微調整や一歩の幅、つまり足元をみてやることができないので、その両足の地図をどうすると筋感覚として普段と似たように身体をつかえるかとか、硬さやその床の揺れみたいのを何度か踏み込んで体感しておいたりとかします。
剣道は、どの床でないといけないということはありません。
どこでも出来るというのもいいことである、、、という良い見方もできます。
ですので、いろいろな床への対応できる、プレイヤーとしての感覚は重要ですし、養われるべきだと思います。
体育のセンセという立場からは、昨今多く作られている剣道場専用の仕様はなかなか多目的として使うことが出来ず、なかなか学校的にはウンと言いがたいところもあるのも事実です。
必修化とかいわれていますけどね、、、これが実際のところ、、、剣道且つ体育のセンセのジレンマ。
また、海外などに行くと板張りであることすらない場合もおおく、おかげで思っきり踏み込むことのできない状況があったりします。
ですから、足の踏み込みが独特な海外の選手がいるのも事実です。

そして、今回は衝撃緩衝が、反動が起こるスプリングではなく、一回で吸収する方法での床の視察・稽古をさせていただきました。
剣道の踏み込み動作は、姿勢・体幹を立て直し、竹刀のスイングをより効果的に行うという効果があると思います。
わたしは、踏み込んでから、スプリングによる反動を使いつつ体勢を作っていたんだなというのを実感しました。
つまり、衝撃を吸収分散されてしまうと、少々キツい感じもあったんですね。
しかし、身体への健康的な観点、技術へ及ぼす影響、体力的なトレーニングとしての効果、などなどと考えてくると、、、いろいろといい面、悪い面がでてくるわけで、解はそう簡単にでないものと思いますし、解がひとつでもないような感じを持っております。
さて、、、摩擦係数などによる滑りの指標、柔らかさの指標(板自体の硬さ、床としての硬さ)、衝撃緩衝の方法とその揺れ方の指標、板ですのでメの向きや、はり方の方向の問題もありましょうし、表面の処理の問題によっては(塗装していなければ)季節・天候による含水率の問題もありましょう。
体育館の規格に関してはJISにあるようですが、剣道場にこのような指標を「剣道場指標」というものがあるといいなぁと思ったんです、今回は。
当然あるとは思うんですが、一般的な体育館規格の延長ではなく、プレイに影響するような意味合いを持たせてもらえるようなものをです。
今回のこの指標の話は、、、その一つを決めて、その条件下ではないと剣道はやってはいけないという話ではありません。
他の種目、たとえば、バレーボールが国際大会を開催するために、体育館内の温度のような環境面まで規定があるとか、サッカーの人工芝や陸上競技場の規格が大会レベルによって色々とあったりとするのと似ているかもしれません。
しかし、どの競技も特定の大会とかに限定している話で、どんな状況でも体育館でバレーボールも、土のグラウンドでもサッカーも陸上も練習するわけですから、剣道もどこでも練習していいということです。
つまりは、こういう指標が明確であれば、、、
・摩擦が高く引っかかる→ケガに注意とか
・選手が独自に持っている感覚も、この数値をみたら、身体感覚を調整できるとか
などというようなことに利用できるのではないかと。
とくにどういう怪我に注意ということを発信できる指標って、いまわたしは指導者でもあるので、欲しいなぁと思います。
さらに、できうれば「剣道に適した範囲」というものを明確にしていければいいのではないかと感じたのです。
その範囲内で、いろいろな効果を明らかにしていければなぁと思ったんです。
こういうのは、学会とかにしても研究課題なんでしょうね…あ、他人事にしてはいけないな(反省)。
他競技とちがって、床との間に靴があるわけではないので、床そのものが身体に技術に影響することは間違いないのですからね。
そして、さらにいうなれば、これは組織として動かないといけない問題かもしれません。
このようなは、剣道具業界にも、同様なことが言えるかもしれません、、、あまりにも業者にまかせっきり感が。
もっとタイアップしていかないといけないなと、、、思うことしかできませんが、思っています。
現状の剣道は、竹刀や剣道具、床がないとできないんですからね。
今回は、ユーザー(使う側)の意見と、今後の剣道のためのちょっとした提案ということですね。
まぁ、まだまだ、床に関しては素人の戯言ですが、、、でも、剣道をしているみなさんにすこしでも考えてもらえる機会を作りたいなと思い、今回のネタにいたりました。
続編がかけるように、こちらも勉強したいと思います。
また、いつか・・・とそういうものがだんだん増えてきました、着装・洗濯・・・お許しあれ。



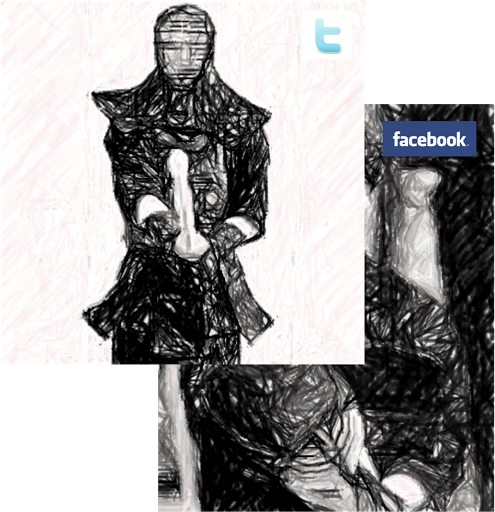


kodamaさん、こちらこそ、いろいろとありがとうございました。
剣道にはらむいろいろな問題点など、視野が広がった感じでいっぱいです。
大変勉強になりました、ありがとうございました。
とにかく、今回のネタはまだまだ素人の戯言のような気がしてなりません。
本来立場的には、こういう選手の感覚を調査しないといけないかもしれませんね。
今後も勉強してまいりたいと思います。
いろいろとご教授ください、ありがとうございました。
先日は、たくさんのご意見をいただきありがとうございました。
凄く研ぎ澄まされた中で稽古されていることが分りました。
今回、このように道場の床について考える機会を作っていただいたことにとても感謝いたします。
また、色々なご意見をお聞かせいただけると嬉しい限りです。
私もしっかりと勉強しておきます。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。